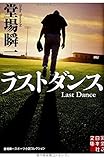ぽんきちさん
レビュアー:
▼
野生動物の数を「適正」に保つ観点から
「狩猟学」。あまり聞かない用語である。
日本においては、明治期に、ドイツ林学の一環として農学系大学に導入されたが、現在では、控えめに言ってあまり顧みられていない学問分野に当たる。
本書の狙いは、この「狩猟学」の入門書となることである。
狩猟対象となる動物の生態学を考慮に入れた上で、野生動物管理の手法として「狩猟」を見直し、そして将来の人材育成も視野に入れ、統合的な野生動物管理システムを作っていこうとするのが大きな目的となる。
記述は学術的ではあるが、さほど難しい専門用語が多いわけでもないので、予備知識がなくても興味があれば読める範囲かと思われる。
狩猟の起源や歴史に始まり、日本における狩猟と野生動物管理の歴史と現状、そしてまた海外の事例を辿る。
専門捕獲技術者の大切さや人材育成する上での問題点等を洗い出し、最終的に、生物多様性を守る支えとなる持続的狩猟とはどのようなものかを考えていく。
なお、本書では他の人々が主張する、オオカミ導入論は却下されている。オオカミがいた江戸時代でもイノシシを防ぐ垣や鉄砲が必要であったし、人を襲う例もずっとあったというのがその論拠だ。
このあたり、どちらの立場が妥当なのかはもう少し議論を要するところだろう。
日本の現在の狩猟法制の元は大正期に改正された狩猟法であるという。ここでは、野生鳥獣の捕獲を一般には禁止し、狩猟対象とされるのは、規則で指定するものとされてなっている。つまり、基本は獲ってはならず、許されたもののみ獲ってもよいということになる。
その後、狩猟法は昭和38年に「鳥獣保護法」となる。当時は狩猟人口の増加に伴い、事故の発生も多く、また野生鳥獣の著しい減少傾向が見られていた。
今日、狩猟人口が激減する中で、「保護」の観点の法では、「有害」とされる鳥獣を抑えきれなくなっている現状が透けて見える。
ドイツやアメリカ、北欧などでは、狩猟者の層が日本より厚い。また一般の狩猟者による狩猟を行政が管理する仕組みが整っており、食肉としての利用も多い。特筆すべきは、狩猟者の年齢層が比較的若いことで、これは高齢化が懸念されている日本とは対照的である。狩猟活動の継続を考えると、絶対数だけではなく、若く将来性のある世代の担い手が必要となる。
驚いたのはアフリカのトロフィーハンティングを紹介する項である。トロフィーハンティングは特権階級の娯楽であり、植民地支配を契機にアフリカにも導入された。対象となる動物は、国によるが、バッファローやライオン、ゾウなどがハンティングされる例も少なくない。保護というよりは、(特に外国人の)狩猟者の欲望、そして外貨獲得の意味合いが大きいようだ。こうした動きにはやはり生態系保全の意味からも監視や規制が必要だろう。
狩猟にはおそらく、ある意味、人の征服欲を満たすような意味合いが付きがちで、だからこそ、狩猟者の「倫理感」や「自律」といったことが大切になってくるのだろう。殺傷能力がある危険な銃器等を扱うわけだから、濫用するようなことがあっては大変である。
本書では、持続可能な狩猟に向けて、専門的捕獲技術者と新人一般狩猟者の育成を提唱している。技術者は高い専門知識を持ち、継続的にその職務を遂行する者。社会的地位が確立されていることが望ましい。たとえば都市部では、安全性の確保が不可欠だが、そうした場所では専門技術者が駆除に当たる。農地や森林のような場所では一般の狩猟者にも入ってもらう。狩猟者が減少している現状から、若い新たな人材を呼び込むために、スクールを作ったり、猟に同行してもらったりという企画も現実に行われている。本書では、そうした動きをさらに活発化させる必要があるだろうとしている。
専門的な判断でどの動物をどのくらい狩るのか計画を立て、実際に狩猟を行う若い人材を増やす。狙いとしてはそのとおりなのだろうが、さまざまな困難がありそうだ。
加えて、生物にはいつでも予測不能な部分がつきまとう。生態系ともなると、多くの生物が関わり合ってくるのでさらに複雑さが増す。
ただ、そこを何とか、探りながらやっていくしか道はないのだろう。
自分で狩猟者になる選択肢がまずないことが申し訳ないようにも思うが、この問題、今後も気に懸けていきたい。
・関連
『山賊ダイアリー(1)』 *5巻まで出ています。リンクはリンク先に。
『オオカミが日本を救う!: 生態系での役割と復活の必要性』
『ジビエを食べれば「害獣」は減るのか―野生動物問題を解くヒント』
*トロフィーハンティングについては、そういえば、山崎豊子『沈まぬ太陽』に出てきていたか・・・。いやぁ、それにしても「今でも」やってるのか。
日本においては、明治期に、ドイツ林学の一環として農学系大学に導入されたが、現在では、控えめに言ってあまり顧みられていない学問分野に当たる。
本書の狙いは、この「狩猟学」の入門書となることである。
狩猟対象となる動物の生態学を考慮に入れた上で、野生動物管理の手法として「狩猟」を見直し、そして将来の人材育成も視野に入れ、統合的な野生動物管理システムを作っていこうとするのが大きな目的となる。
記述は学術的ではあるが、さほど難しい専門用語が多いわけでもないので、予備知識がなくても興味があれば読める範囲かと思われる。
狩猟の起源や歴史に始まり、日本における狩猟と野生動物管理の歴史と現状、そしてまた海外の事例を辿る。
専門捕獲技術者の大切さや人材育成する上での問題点等を洗い出し、最終的に、生物多様性を守る支えとなる持続的狩猟とはどのようなものかを考えていく。
なお、本書では他の人々が主張する、オオカミ導入論は却下されている。オオカミがいた江戸時代でもイノシシを防ぐ垣や鉄砲が必要であったし、人を襲う例もずっとあったというのがその論拠だ。
このあたり、どちらの立場が妥当なのかはもう少し議論を要するところだろう。
日本の現在の狩猟法制の元は大正期に改正された狩猟法であるという。ここでは、野生鳥獣の捕獲を一般には禁止し、狩猟対象とされるのは、規則で指定するものとされてなっている。つまり、基本は獲ってはならず、許されたもののみ獲ってもよいということになる。
その後、狩猟法は昭和38年に「鳥獣保護法」となる。当時は狩猟人口の増加に伴い、事故の発生も多く、また野生鳥獣の著しい減少傾向が見られていた。
今日、狩猟人口が激減する中で、「保護」の観点の法では、「有害」とされる鳥獣を抑えきれなくなっている現状が透けて見える。
ドイツやアメリカ、北欧などでは、狩猟者の層が日本より厚い。また一般の狩猟者による狩猟を行政が管理する仕組みが整っており、食肉としての利用も多い。特筆すべきは、狩猟者の年齢層が比較的若いことで、これは高齢化が懸念されている日本とは対照的である。狩猟活動の継続を考えると、絶対数だけではなく、若く将来性のある世代の担い手が必要となる。
驚いたのはアフリカのトロフィーハンティングを紹介する項である。トロフィーハンティングは特権階級の娯楽であり、植民地支配を契機にアフリカにも導入された。対象となる動物は、国によるが、バッファローやライオン、ゾウなどがハンティングされる例も少なくない。保護というよりは、(特に外国人の)狩猟者の欲望、そして外貨獲得の意味合いが大きいようだ。こうした動きにはやはり生態系保全の意味からも監視や規制が必要だろう。
狩猟にはおそらく、ある意味、人の征服欲を満たすような意味合いが付きがちで、だからこそ、狩猟者の「倫理感」や「自律」といったことが大切になってくるのだろう。殺傷能力がある危険な銃器等を扱うわけだから、濫用するようなことがあっては大変である。
本書では、持続可能な狩猟に向けて、専門的捕獲技術者と新人一般狩猟者の育成を提唱している。技術者は高い専門知識を持ち、継続的にその職務を遂行する者。社会的地位が確立されていることが望ましい。たとえば都市部では、安全性の確保が不可欠だが、そうした場所では専門技術者が駆除に当たる。農地や森林のような場所では一般の狩猟者にも入ってもらう。狩猟者が減少している現状から、若い新たな人材を呼び込むために、スクールを作ったり、猟に同行してもらったりという企画も現実に行われている。本書では、そうした動きをさらに活発化させる必要があるだろうとしている。
専門的な判断でどの動物をどのくらい狩るのか計画を立て、実際に狩猟を行う若い人材を増やす。狙いとしてはそのとおりなのだろうが、さまざまな困難がありそうだ。
加えて、生物にはいつでも予測不能な部分がつきまとう。生態系ともなると、多くの生物が関わり合ってくるのでさらに複雑さが増す。
ただ、そこを何とか、探りながらやっていくしか道はないのだろう。
自分で狩猟者になる選択肢がまずないことが申し訳ないようにも思うが、この問題、今後も気に懸けていきたい。
・関連
『山賊ダイアリー(1)』 *5巻まで出ています。リンクはリンク先に。
『オオカミが日本を救う!: 生態系での役割と復活の必要性』
『ジビエを食べれば「害獣」は減るのか―野生動物問題を解くヒント』
*トロフィーハンティングについては、そういえば、山崎豊子『沈まぬ太陽』に出てきていたか・・・。いやぁ、それにしても「今でも」やってるのか。
掲載日:
外部ブログURLが設定されていません
投票する
投票するには、ログインしてください。
分子生物学・生化学周辺の実務翻訳をしています。
本の大海を漂流中。
日々是好日。どんな本との出会いも素敵だ。
あちらこちらとつまみ食いの読書ですが、点が線に、線が面になっていくといいなと思っています。
「実感」を求めて読書しているように思います。
赤柴♀(もも)は3代目。
この夏、有精卵からヒヨコ4羽を孵化させました。そろそろ大雛かな。♂x2、♀x2。ニワトリは割と人に懐くものらしいですが、今のところ、懐く気配はありませんw
この書評へのコメント
- ぽんきち2014-12-21 23:01
本書にも取り上げられていた「おおち山くじら」の事例を紹介する記事です。
<イノシシと農家が闘う時代は終わろうとしている(長濱世奈・ハフィントンポスト)>
http://www.huffingtonpost.jp/sena-nagahama/post_8765_b_6339996.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
さまざまな試みがこの例のようにうまく回っていくとよいですが。
*山くじらというと、広重のこの絵を思い出しますね。
「びくにはし雪中」
https://www.adachi-hanga.com/ukiyo-e/items/hiroshige185/クリックすると、GOOD!と言っているユーザーの一覧を表示します。 
コメントするには、ログインしてください。
書評一覧を取得中。。。
- 出版社:朝倉書店
- ページ数:154
- ISBN:9784254450286
- 発売日:2013年01月23日
- 価格:3456円
- Amazonで買う
- カーリルで図書館の蔵書を調べる
- あなた
- この書籍の平均
- この書評
※ログインすると、あなたとこの書評の位置関係がわかります。